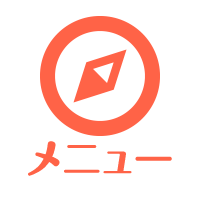元素ファミリー 日本の硬貨に使われる元素たち
硬貨とは,金属でできた貨幣のことです。これらの硬貨はどのような金属でできているのでしょうか。
1円硬貨
 写真1 1円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)
写真1 1円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)銅を含まない唯一の硬貨で,純粋なアルミニウムからできています。
また,さびているのを見たことがないと思いますが,実は目に見えないだけで,表面は薄くさびています。そのさびが非常に安定で,内部のアルミニウムを守っているため,それ以上さびなくなっているのです。
1円硬貨をつくる製造原価(コスト)については諸説ありますが,公表されていません。
5円硬貨
 写真2 5円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)
写真2 5円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)銅(60~70%)と亜鉛(30~40%)からできている,黄銅と呼ばれる合金ですが,真鍮といったほうが身近でしょうか。
銅に亜鉛を混ぜると,融点が低くなるなど鋳造しやすくなるため,複雑な形のものをつくるのに向いており,金管楽器にも使われています。ブラスバンドのブラス(brass)は黄銅のことです。
10円硬貨
 写真3 10円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)
写真3 10円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)銅(95%)と亜鉛(3~4%)とスズ(1~2%)からできている,青銅と呼ばれる合金です。青銅色というと,青と緑の中間のくすんだ色を思い浮かべると思いますが,実際の青銅は混ぜる割合によって色が大きく変わります。10円硬貨はスズの割合が低いので銅本来の色にかなり近いのです。
銅メダルを英語でブロンズメダルと言いますが,ブロンズ(bronze)は青銅のことです。
50円硬貨・100円硬貨
 写真4 50円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)
写真4 50円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局) 写真5 100円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)
写真5 100円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)銀色なので銀でできていると思いきや,実は銅(75%)とニッケル(25%)からできている,白銅と呼ばれる合金です。
1966年まで製造されていた50円硬貨は純粋なニッケル,100円硬貨は銀が主成分(60%)でしたが,1967年から,白銅が使われるようになりました。また,1999年まで製造されていた,初代500円硬貨も白銅が使われていました。
500円硬貨
 写真6 500円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)
写真6 500円硬貨(写真提供:独立行政法人造幣局)外側は銅(72%)と亜鉛(20%)とニッケル(8%)からできている,ニッケル黄銅と呼ばれる合金で,中央は50円硬貨・100円硬貨と同じ白銅,そして目には見えませんがその内部に純粋な銅があります。つまり,銅を白銅ではさみ,それをニッケル黄銅の輪にはめてつくっているのです。さらに,つくりにも非常に高い技術が用いられ,偽造を防いでいます。ぜひ,いろいろな角度から見てみてください。
また,2021年6月20日まで製造されていた旧500円硬貨もまだ目にする機会があるでしょう。これは全体がニッケル黄銅でできています。
以上のように1円硬貨以外の硬貨は全て銅が使われています。銅が,金属の中ではやわらかいので加工しやすいことや,融点が低い上に他の金属と合金をつくりやすいこと,細菌類のはたらきを抑え繁殖を防ぐ働き(微量金属作用といいます)を持っており,表面を清潔に保てることがその理由です。
化学だいすきクラブニュースレター第57号(2024年7月1日発行)より編集/転載