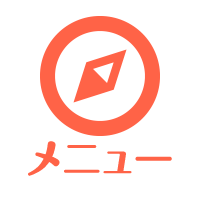私と化学(株式会社レゾナック フェロー・酒井浩志)
長野県出身の私は,中学時代から写真を撮ることが大好きです。中学の担任の化学の先生が写真愛好家だった影響で,私もシャッターを切る楽しさに目覚め,その後50年も続く趣味となりました。
みなさんはフィルムカメラというものを知っていますか? 今の時代スマホで簡単に写真を撮り,その場ですぐに見られますが,私が中学生の頃はフィルムカメラしかありませんでした。フィルムカメラは,その場ですぐに写真を見ることができず,フィルムを現像し,その後,ネガから印画紙に引き伸ばしを行う必要がありました。この一連の作業は暗室で行われ,実は化学の原理が大いに関わっているのです。フィルムや印画紙には,光に反応する感光材料が塗布されており,その主成分はハロゲン化銀(AgBrなど)です。それでフィルムカメラは銀塩カメラとも呼ばれています。
写真を撮り始めるようになってすぐに,先生から白黒写真の現像方法を教えてもらいました。自分の部屋の押入れを暗室に改造し,そこで写真の現像に没頭しました。ネガをセットし,印画紙に露光します。その印画紙をトングで挟んで現像液の中でゆっくりと揺らします。赤い暗室ランプの下で徐々に白黒の像が浮かび上がる瞬間はいつもワクワクしました(特に思い通りの画像が現れた時はガッツポーズでした!)。そして印画紙を現像液から停止液に移し,現像を止めます。この停止液には酢酸が使われていたため,現像の日は部屋中に酢酸の匂いが充満しました。特に長野県の冬は寒く,現像を正確にコントロールするには,現像液を適切な温度に保つ必要があり,温度が化学反応にどのように影響するのかを体験しました。
このフィルムの現像から引き伸ばしまでのプロセスは,私にとって化学との最初の出会いであり,化学への興味を深めるきっかけとなりました。その興味は,大学で応用化学を学ぶ動機となり,研究室では導電性高分子を用いたリチウム二次電池の研究を行いました。実験で面白いデータが出てくる時はワクワクしました。その気持ちは,大人になっても変わることはなく,その後,化学会社でハードディスクの製品開発をする際も,ワクワク感は私の原動力となりました。
化学だいすきクラブのみなさんも,どうぞワクワク感を大切にしてください。そして化学の楽しさをたくさん味わってもらいたいと思います。
化学だいすきクラブニュースレター第57号(2024年7月1日発行)より編集/転載